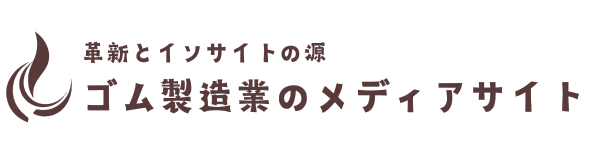工程能力指数CPKの基礎から計算式まで徹底解説|品質管理で失敗しない完全ガイド
製造業における品質管理では、「工程が安定して規格を満たしているか」を数値で確認する必要があります。
その代表的な指標が工程能力指数(CPK)です。
この記事では、CPKの定義から計算式、実務での活用方法まで詳しく解説します。
品質保証や工程改善に携わる方にとって必読の内容です。
工程能力指数(CPK)とは?
CPKとは、製造工程が設計規格(上限・下限)に対してどれだけ安定して製品を作れているかを示す指標です。
工程能力を表す指数にはCpk、Cpなどがありますが、特にCpkは平均値の偏りも考慮した実務的な指数として用いられます。
- 工程の平均値が中心にあるかどうか
- 規格範囲に対してばらつきが小さいかどうか
- 顧客要求に安定して応えられるか
CPKの基準を正しく理解することは、量産立ち上げや品質保証の現場で極めて重要です。
CPKの計算式
CPKは、以下の計算式で求められます。
CPK = min{ (USL - μ) / (3σ), (μ - LSL) / (3σ) }
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| USL | 規格上限値 |
| LSL | 規格下限値 |
| μ | 工程の平均値 |
| σ | 工程の標準偏差 |
この計算式からわかる通り、工程が規格の中心からずれていた場合でも、その偏りを考慮して指数を算出できます。
CPKの目安と基準値
一般的に、CPKの値が高いほど工程は安定しているとされます。
具体的な目安は以下の通りです。
| CPK値 | 工程の状態 |
|---|---|
| 1.33以上 | 十分に安定(顧客要求を満たせる) |
| 1.0〜1.33 | やや不安定(改善の余地あり) |
| 1.0未満 | 規格外リスク大(要改善) |
特に自動車や医療機器といった高い信頼性が求められる業界では、CPK≧1.67を基準とする場合もあります。
各業界の品質基準については、
JIS(日本産業規格)の公式サイトで詳細が確認できます。
CPK活用の具体的なシーン
実際の製造現場でCPKが活用される場面を整理します。
- 新規ライン立ち上げ時の妥当性確認
- 金型や設備更新後の工程評価
- 顧客への品質保証データ提出
- 量産中の品質トラブルの予兆検知
特にゴムや樹脂成形など、ばらつきが出やすい分野ではCPKの管理が有効です。
CPKを改善するためのアプローチ
CPKを高めるためには、「平均値を規格中心に近づける」「ばらつきを減らす」という2つの方向性があります。
具体的な手法を以下に示します。
- 工程条件の最適化(温度・圧力・速度など)
- 治工具の精度向上
- 作業標準の明確化と教育
- 定期的な統計的工程管理(SPC)の導入
また、ばらつきの原因を解析する際には、魚骨図や回帰分析などの品質管理手法が役立ちます。
よくある質問(FAQ)
まとめ
CPKは、工程の安定性と顧客要求への適合度を同時に評価できる有効な指標です。
本記事では、CPKの定義、計算式、基準値、活用シーン、改善方法まで徹底的に解説しました。
実務で活かす際は、単に値を求めるだけでなく、工程改善や品質保証にどうつなげるかを考えることが重要です。